
春田 壮史(東京学芸大学附属国際中等教育学校・2019年入学)
法律を使うことによって、人を助けられると思い、法律学科に入学しました。本学科では、憲法や民法、刑法といった基本的な法分野について学修したうえで、演習(ゼミナール)形式の授業でその分野を深く検討したり、新たな法分野での問題を扱ったりすることができます。
私は、刑法の演習に所属し、毎回、裁判所の判決を複数検討することによって、問題の本質的な部分を理解し、そこでの対立点を明確にしたうえで、その対立点を解消するための方法を議論しています。解決策は一つとは限らず、複数考えられることもありますし、どれも選んで正解ということも往々にしてあります。この「正解のない問題」に対して、最善の答えを導き出していくことについて、これ以上に面白いことはないと感じています。将来は、このような問題に日々携わる、裁判官や検察官、弁護士(法曹といわれる職業)を目指しています。
本学科では、法曹を目指す学生も多く、同じ志を持つ仲間と自主的に演習を組んで、裁判所の判決について検討しています。公務員や民間企業に就職する学生も多いため、彼らと日常的にコミュニケーションを取ることにより、同じ問題について別の観点からのアプローチを得ることができ、刺激的な毎日を送っています。

髙橋 理紗(雙葉高・2018年入学)
様々な分野でグローバル化が叫ばれる中、世界が一体となってめざす理想の世界を実現するため変容し続ける国際法に興味を持ち、国際関係法学科に入学しました。一括りに国際法といってもその内容は多岐にわたっており、本学科では総論・各論をはじめ、紛争解決、経済、国際取引など様々な視点から国際法を学ぶことができます。また、外国法(英米法、ドイツ法など)も選択できます。
学習の進め方として、基本的な国内法の知識を1・2年次で身に着けつつ、2年次から国際法の学習をはじめ、3年次以降は各個人の興味に合わせそれぞれの学びを深めていくことになります。学科同士の垣根が低く、国際関係法学科に所属していながら他学科の授業を取ることができるため、本学科から法曹を目指す人や、環境法のゼミに入る人もおり、自分の分野にとらわれず学びたいことみつけ、深めることができます。私自身も刑法のゼミで勉強する予定です。
本学科の学生は、それぞれ目指すものを持ちそのために留学するなど積極的に行動を起こしている人が多く、お互い刺激しあい成長できることが一つの魅力だと思います。また、意見を交換し合うことに前向きであり、その中で国際意識を高めつつ自分の思考の幅を広げることができるため、国際社会を法的視点から見たいと思う人には最適の環境です。
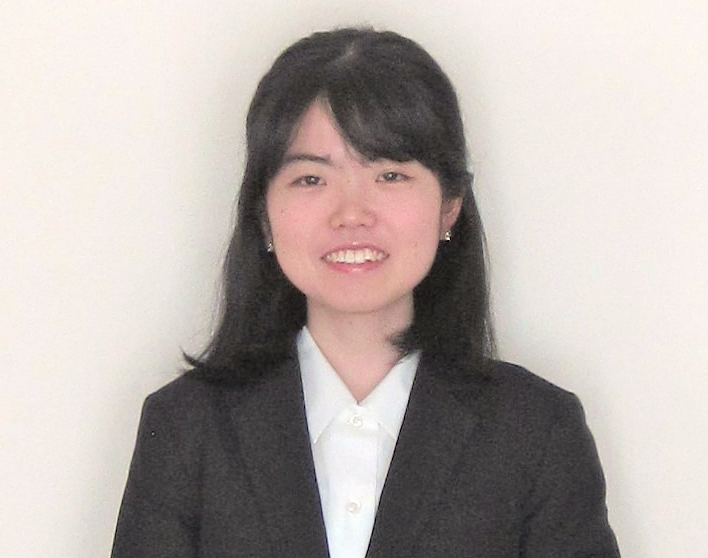
小谷野 有以(山手学院高・2019年入学)
深刻化する環境問題の現状や解決の方法について、法的観点から学びたいと考え、地球環境法学科に入学しました。
私たちの生活に不可欠な基盤である地球環境を守り維持するために、法律は非常に重要な存在です。悲惨な公害被害や規制違反の是正を背景に、法令の制定や改正、裁判例が蓄積され、今なお発展を続けているのが環境法の魅力の1つです。
本学科には、各分野の環境法の専門の先生が在籍されており、自分の興味に合わせて学びを深めることができます。1・2年次で学ぶ憲法や民法、行政法の基礎知識をもとに、廃棄物やリサイクル、自然保護、企業と環境などの身近な問題と環境法について勉強したり、損なわれた環境の回復や、被害者の救済の方法を過去の裁判例に学んだりと、多角的に環境問題に触れることができます。また、現役の弁護士の先生から、実務を踏まえたお話を聞くこともできます。気候変動や生物多様性の保全といった国際的な環境問題に関する法律や条約、EUやアメリカなどの外国の環境政策に関する講義も充実しています。
環境法は、事後対応ではなくより未然防止的に、現在だけではなく将来世代の利益を含めた広い視野から、環境の保護を目指しています。環境問題の内容が多様化し、影響が及ぶ地域や世代が拡大する中で、現代社会を生きる人として持つべき知見を得られる場所だと思っています。

漆原 香奈恵(2023年度入学)
私たちは生活の様々な場面で年金・医療・介護・子育て・高齢者や障害者への福祉サービスなどの社会保障制度を利用しています。
社会が大きく変化し、社会保障制度は、少子高齢化の進展、雇用環境の変化、家族形態や地域基盤の変化などの問題に直面し、持続可能性の確保と機能強化が求められています。
私は、社会保険労務士として開業しながら上智大学大学院で社会保障法を専攻しています。実務において注力してきた社会保険(特に障害年金)・社会福祉を法学の視点から歴史的・理論的かつ実体的に考察し、もっとよくするために制度・運用などを社会全体の中で捉え、研究を深めていきたいと思っています。
上智大学大学院は少人数制の講義となっており、先生方は学生の研究内容や希望に応じて柔軟に対応してくださいます。講義では疑問や意見を互いに議論でき、それによって新たな発見をすることができます。また、研究テーマや実務に関連する他の研究科の講義も履修できるところも魅力的です。
指導教員の先生には、常勤の学生向け課題研究の履修相談や仕事との両立など細やかにご配慮いただいています。支えてくれている家族や職場のスタッフ達、恵まれた環境を提供してくださる大学院に感謝しながら、研究に取り組んでいきます。

秋山 俊大(2023年度入学)
我が国における安全保障の基本方針である国家安全保障戦略において「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面」と表現される現在の日本を取り巻く安全環境の中、我が国の平和と安定の確保のために法の秩序に基づく国際秩序の安定が求められています。
私は上智大学大学院(法学研究科)において防衛省航空自衛隊に所属しつつ、博士前期課程の学生として国際法の研究をしています。
特に国際法の中でも実務経験を背景に「条約解釈の視点を中心とした国際人道法(International Humanitarian Law)における軍事目標(Military Objectives)の定義及び付随的損害(Collateral Damage)の考え方」を研究の対象としており、今後更に厳しくなることが予想される国際秩序及び地域秩序の安定の一助になればとの気概を持って日々研究に取り組んでいます。
上智大学大学院では所属している学部・研究科に限定されず、様々な講義に参加することができます。私は国際関係論の講義も受講しており、多角的な視点から研究に取り組むきっかけにすることが出来ているともに私の研究テーマに合わせた専門的な知見からのアドバイスなど、受講している講義でも細やかな指導を頂いております。
まさに「学べば則ち固ならず。」を実感する毎日です。
社会人という立場で同じ研究室の仲間たちと研究に取り組めているのは大学院、職場など多くの方に支えられていることは言うまでもありません。感謝の気持ちを忘れず、微力ながら我が国の安全保障環境のあるべき姿を実現できるように研究に取り組んでいきたいと思います。

田中 友也(2024年度入学)
2024年度に博士前期課程に入学し、民事手続法を専攻している田中友也と申します。
学部生の時に民事訴訟法のゼミに入り、そこで、指導教官の先生の「当事者主義」に重点を置いた民事手続法へのアプローチに惹かれ、大学院への進学を決意しました。
上智大学大学院法学研究科の講義では、学部のゼミのような少人数制のスタイルをとっており、場合によっては先生方とマンツーマンでの講義となる可能性もあります。こう書くと些か権威主義的に見えるかもしれませんが、その法学分野で傑出した研究成果を出しておられる先生方のお時間を独占して指導していただける機会があるというのはとても贅沢なことであり、大学院法学研究科でしか体験することができない魅力的なポイントであると考えています。
また、身の回りで起きた事象やニュースに関して、それぞれの異なる専攻分野の法的知識を交えながら法学研究科の仲間達と議論したり、実務家として働いておられる方々から実務家の視点を通した意見やアドバイスをいただけるのも法学研究科ならではの醍醐味と言えるでしょう。
刻一刻と変化していく我々を取り巻く環境に対応していく地力を養うために、学部卒業後には上智大学大学院法学研究科で研究し、学びを深めるという選択肢はいかがでしょうか?
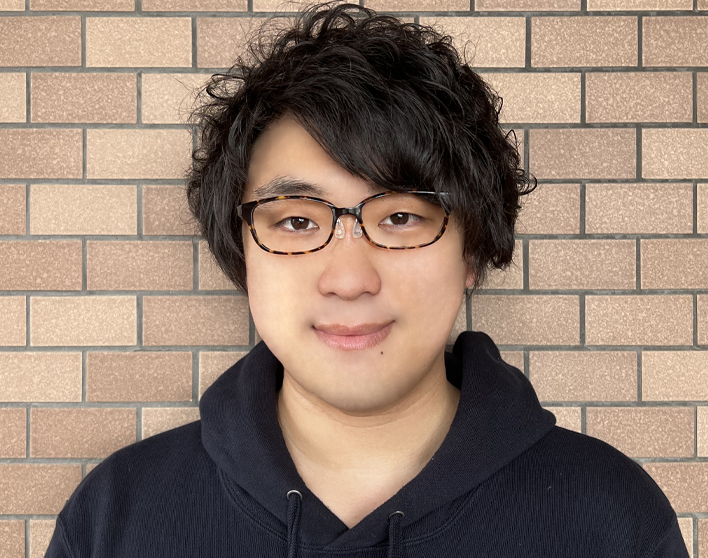
原田 悠太郎(2024年度入学)
近年、“個性”や“多様性”のような「人格」に関するキーワードがブームになっているようです。前提未検証の主張は論理的にも成立し得ないので、“個性”や“多様性”言説には、「人格」の存在についての確固たる確証・根拠があるのでしょう。もちろんこの確証は、当人がそう言い張っているとか、他者が勝手に当人をそういう「人格」であると決め付けているとか、その手のいかようにも操作可能である、短絡的で粗末な根拠に基づくものではないに違いありません。
今のところ私はそのような確証や根拠を知らないので、「人格」概念について勉強しています。少なくとも自らによる、あるいは他者によるレッテル貼りによって現れる「人格」は虚構であり、むしろ他者を抑圧し、侵害すらしうる無用の長物です。何かしらのルールを粗末なレッテル貼り以外で成立させるためには、そもそもの「人格」について検証すべきでしょう。
指導教員の先生は、フラットな立場で議論に付き合ってくださります。ある主張について「AはAである、なぜならAだからである」というのは世間ではワガママと呼ばれ、相手にすらされないレベルの難癖になってしまいます。指導教員の先生が(反対意見も含めた)先行研究も踏まえて指導してくださることは、私にとって大きな刺激と戒めになっています。
私の指導教員の先生は、大学院への入学を“入院”と表現していました。本来、“入院”の必要性などないほうが良いのでしょうが、ワガママを放言して害悪を撒き散らすよりは、せめて“入院”の必要性を自覚している分、私はまだマシなのかもしれません。